- ホーム
- 行政書士いしなぎ事務所
- ブログ
- 帰化申請に必要な書類を徹底解説|取得方法・翻訳・行政書士のサポートまで【2025
帰化申請に必要な書類を徹底解説|取得方法・翻訳・行政書士のサポートまで【2025
- 2025/06/25
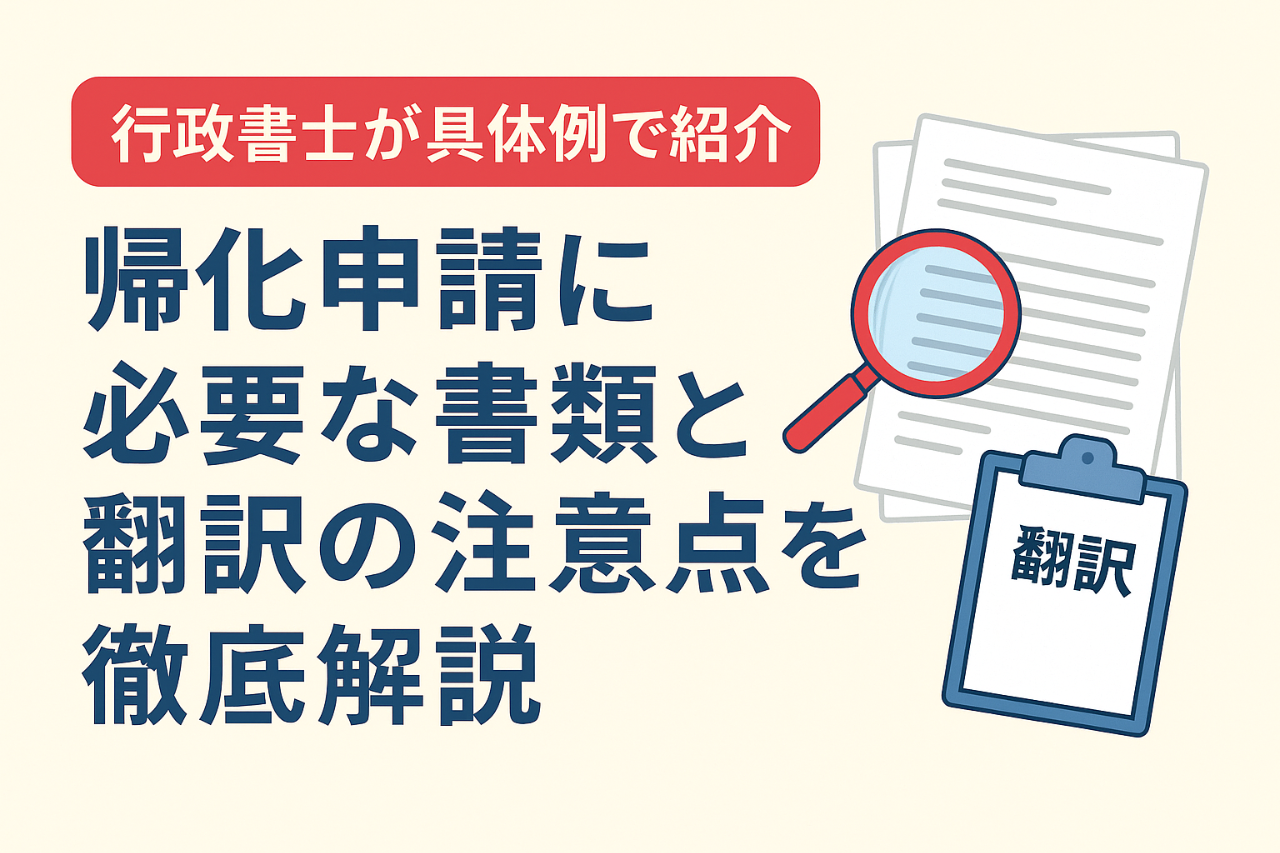
帰化申請に必要な書類と翻訳の注意点を徹底解説
日本での帰化申請を考えるとき、最初の大きなハードルとなるのが「必要書類の準備」と「外国語書類の翻訳」です。特に外国籍の方が母国で発行された書類については、取得方法や翻訳ルールが分かりにくく、時間も労力もかかる作業となります。この記事では、行政書士いしなぎ事務所が実際の面談経験をもとに、書類準備や翻訳のポイントを具体的にわかりやすく解説します。
英語版(English version)はこちらからご覧いただけます。
目次
📑 書類別ナビゲーション

- 帰化許可申請書
- 履歴書
- 原国籍のパスポート・在留カードのコピー
- 住民票(世帯全員)
- 原国籍のパスポート・在留カード
- 納税証明書
- 所得証明書(課税証明)
- 勤務証明書または在籍証明書
- 預金通帳の写し
- 賃貸契約書の写し
- 家族関係証明(外国語)
- 翻訳文
- 理由書
📄 必要書類一覧と取得方法【保存版】

以下に帰化申請でよく必要となる書類をリストアップし、それぞれの入手方法・注意点・行政書士の関与について詳しく解説します。
帰化許可申請書
入手方法法務局の窓口で、事前相談後に「本人にのみ」直接手渡されます。行政書士でも代理取得はできません。インターネットからのダウンロード不可。
注意点- 書式が個別に対応されるため、事前相談が必須です。
- 本人による署名欄があるため、代筆不可。
- 面談後に数日かけて作成される場合もあり。
- 記載内容の作成補助・チェックは可能。
- 交付そのものは本人対応。
履歴書
入手方法法務局での面談時に配布されることが多く、申請者本人が記入。
注意点- 学歴・職歴を正確に記載。空白期間がないように。
- 日本語で記載、誤字・脱字に注意。
- 本人へのヒアリングをもとに原案作成サポート。
- 内容チェック・整合性確認が可能。
原国籍のパスポート・在留カードのコピー
入手方法本人が自宅やコンビニなどでコピーを取る(カラー推奨)。
注意点- 在留カードは表裏両面のコピーが必要。
- パスポートは全ページ(特に査証欄)をコピー。
- コピーの確認や不足ページの指摘が可能。
住民票(世帯全員)
入手方法市区町村役所またはコンビニ交付(マイナンバーカード必要)で取得可能。
注意点- 続柄の記載が必要。
- マイナンバーの記載は不要(除外)。
- 3ヶ月以内に取得したもの。
- 本人の委任状があれば代理取得可能。
原国籍のパスポート・在留カード
入手方法本人の手元にある現物をコピー。両面のコピーが必要。
注意点- コピーはプリンターやコンビニでの印刷で可。
- パスポートは過去のものも可能な限り提出する。
- 鮮明なコピーでないと差し戻されることがある。
- コピー方法の助言が可能。
- 確認チェックと補足資料の作成支援。
納税証明書
入手方法税務署または市区町村役所にて本人申請。国税は税務署、市民税は市役所。
注意点- 所得税・住民税ともに直近2〜3年分が必要な場合がある。
- 税務署の様式委任状での取得が原則必要。
- 印鑑が必要な場合あり。
- 委任状作成・様式案内。
- 申請書の記入補助。
- 取得代行(委任状がある場合に限る)
所得証明書(課税証明)
入手方法市区町村役所で取得。本人または行政書士による委任取得が可能。
注意点- 複数年分を求められる場合がある。
- 3ヶ月以内の発行日である必要がある。
- マイナンバーカードを利用したコンビニ交付が可能な自治体もある。
- 必要年度の確認と案内。
- 委任取得対応(委任状必要)。
勤務証明書または在籍証明書
入手方法勤務先(人事・総務部など)に発行を依頼。
注意点- 会社の代表印または社判が必要な場合あり。
- 雇用形態、勤務期間などを正確に記載してもらう。
- 依頼文テンプレートの提供。
- 記載内容のチェック・助言。
預金通帳の写し
入手方法本人の手元にある通帳をコピー。直近6ヶ月分が望ましい。
注意点- 残高だけでなく入出金の履歴も提出対象となる。
- ネットバンキング利用者はPDF明細でも可。
- コピー範囲のアドバイス。
- 補足説明文の作成支援。
賃貸契約書の写し
入手方法契約時の書類を本人がコピー。
注意点- 住所と契約者名義が一致しているページのみでよい。
- 契約期間が切れている場合は更新書類も提出。
- 記載内容の確認と補足書類の提案。
- 必要範囲のアドバイス。
家族関係証明(外国語)
入手方法母国の戸籍機関等で取得(大使館・領事館経由含む)。
注意点- 出生証明・婚姻証明・離婚証明などが該当。
- 翻訳文の添付が必要。
- 一部国では英語文の発行も可能。
- 取得方法や必要書類の案内。
- 翻訳または翻訳文の確認・署名支援。
翻訳文
入手方法本人が作成するか、行政書士など専門家に依頼。
注意点- 誤訳や表現の不一致があると申請不利になる場合がある。
- 翻訳者の記名・署名が必要。
- 行政書士による翻訳代行可。
- 申請書類全体との整合性チェック。
理由書
入手方法本人の動機をもとに作成。ヒアリングに基づき行政書士が作成支援。
注意点- 帰化動機は具体的・前向きな表現が望ましい。
- 日本語能力が低い方の場合は補足説明が必要な場合も。
- ヒアリングに基づき内容を整理・構成。
- 申請全体の文脈と矛盾がないかを確認。
📎 書類提出時の形式・まとめ方について

帰化申請書類は、順番通り・整った状態で綴じて提出する必要があります。法務局ごとに細かい指示があることもありますが、以下は一般的な提出形式です。
📄 書類の並び順(標準的な例)
※事前相談時に「提出書類一覧表」が交付されますが、以下は多くの法務局で指定される一般的な並び順です。
🧷 書類のまとめ方・装丁のポイント
- ホチキス止めは原則禁止:書類はバラで提出します(クリアファイルや封筒に入れて渡す形)
- 書類の角を折らない/破らない:丁寧に扱い、すべての用紙はA4に統一
- 順番どおりに提出:混在や逆順は審査の遅延につながるため注意
- 原本がある場合はコピーとセットで:原本は返却されるケースもあるが、必要に応じてコピーを添える
- 翻訳文と原文は一体化:紙でホチキスせず、重ねて並べて提出(ファスナーやバインダーも不要)
📎 提出時の書類の量と確認ポイント
- 提出書類は100〜200枚以上になることが多く、書類の順序や漏れがあると差し戻しになる可能性も
- 提出チェックリストを作成し、すべての項目にチェックを入れておくと安心
- 法務局によっては副本(写し)の提出を求められることもあるので、全書類のコピーを控えとして保存することが推奨
🗂 ファイル・封筒での提出例
- A4のクリアファイルに書類を順番に入れて提出
- 表紙は不要(法務局で不要と言われることが多い)
- 封筒に入れる場合は角2封筒で、申請者名を記入
